コラム
第3回
ずいぶん前に、有名ラーメン店に入った際のことである。濃厚なスープと太麺が売り物で、連日、長蛇の列ができる人気店だった。
店主は、いわゆる「ガンコ店主」タイプで、マスコミなどにも登場している人だった。その店主が、ミスをした修行中の従業員を、カウンター内で、大声で何度も叱りつけ始めた。パワハラの典型だった。店内は注文を伝える声もやみ、店主の声だけが鳴り響いていた。
店主の目の前の席で食事をしていた男性が、「怒鳴るなら裏でやってもらえないですか。落ち着いて食べられない」と言った。すると、経営者は「これはうちのやり方なんだ。文句があるなら出て行ってくれ。お代はいらない」と大声で言い返し、そのまま男性を追い出してしまった。
偶然、居合わせただけだが、こちらもいい気分ではない。行列待ちして、ようやく食べ始めたところだったが、無言で箸を置き、勘定を済ませて外に出た。
果たして、男性はクレーマーだったのだろうか。それとも、お店側に、お客の声を聞く姿勢が足りなかったのだろうか。
東京都が4月から施行するカスタマー・ハラスメント防止条例についてである。
今回の条例でポイントとされているのはカスタマー・ハラスメントの判定基準。「カスハラだと、どう判断するのか」が問題だ。
都の「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針」では、カスハラについて「働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすもの」と述べている。また、就業者の業務内容によって顧客等との接し方が異なる点について十分に留意するよう、促している。
それを店主の側から見ると「マスコミにも出るガンコ店主」の演出が業務内容だとして、「声を抑えさせる要求は事業イメージを損なう、妥当ではない要求であり、事業継続に悪影響を及ぼす迷惑行為」と主張できてしまう。
もちろん、店主の怒鳴り声にも、男性に対する対応にも、賛同できない。しかし、今回の条例やガイドラインだけでは、このケースでさえ解釈が難しい。
コンタクトセンターはカスハラを受けやすい職場だ。しかし、応対中に、通話内容がカスハラ認定基準に達したかが明確でない状況で、カスハラだと判定してオペレータを守るのは難しい。また、実際のところ、明確にカスハラと判定できるケースより、基準のボーダーライン上でオペレータの対応の隙を突こうとする相手ほど、実はオペレータを精神的に追い込むのである。
だからといって、コンタクトセンター側が一方的にカスハラと決めつけることはできない。それでは、くだんのラーメン店のようにお客さまを追い出すコンタクトセンターが現れかねない。
今回の条例は、間違いなくオペレータ保護の第一歩であり、全国的にも試金石となる。だからこそ、コンタクトセンターの運営側にも、社会通念的に納得されるカスハラ判定基準を確立することが、いま求められている。
2025年03月20日 00時00分 公開
2025年03月20日 00時00分 更新
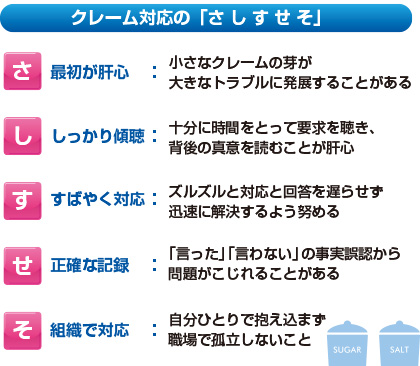
元ファーストクラスCAの接客術“おもてなし力”の磨き方
2025年5月号 <元ファーストクラスCAの接客術 “おもてなし力”の…
江上 いずみ

[製品紹介] Beluga Box SaaS / シーエーシーPR

現場を守り、優良顧客を守る 「カスハラ対応」の極意
2024年11月号 <現場を守り、優良顧客を守る 「カスハラ対応」の極…
齊木茂人
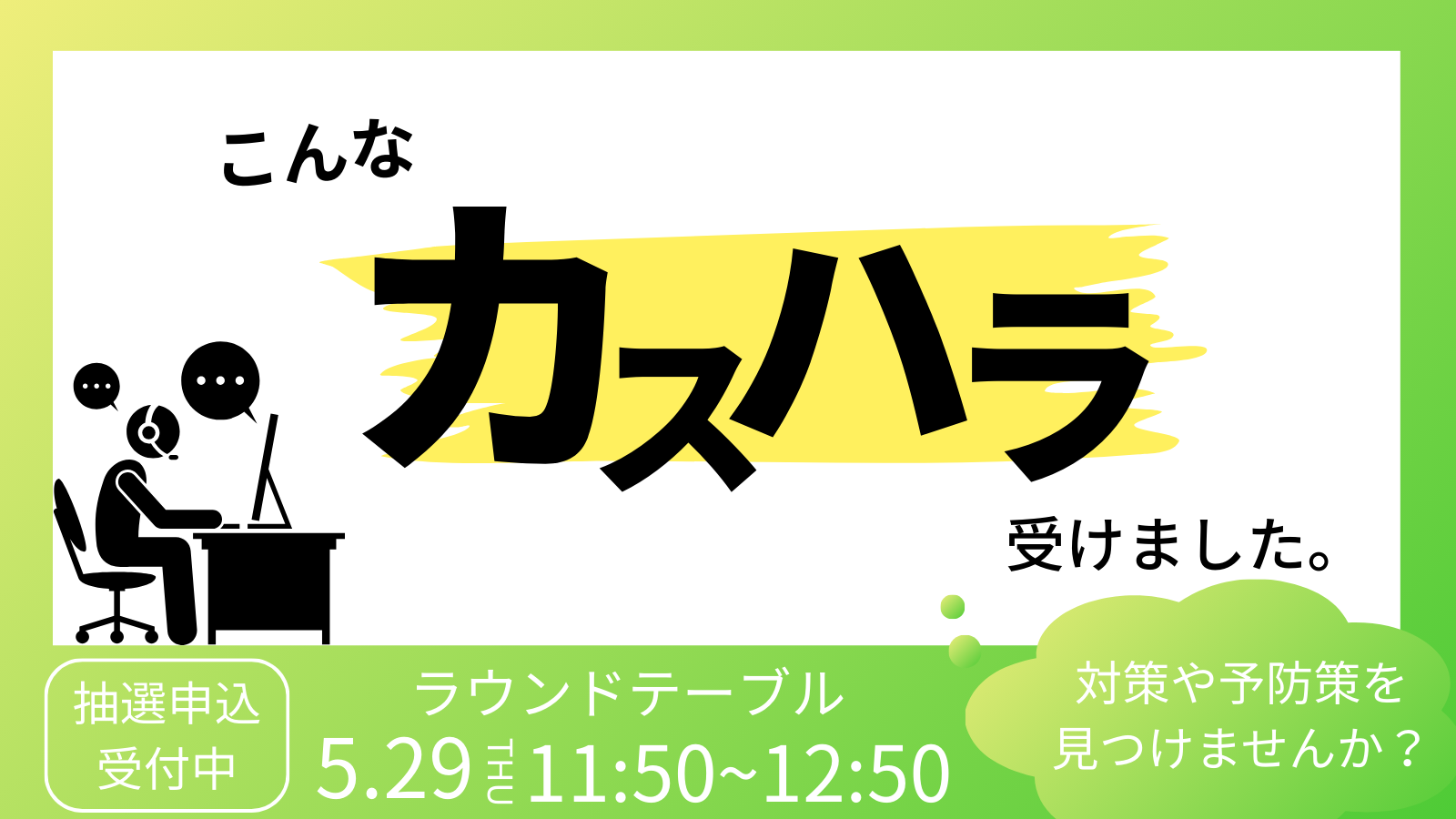
カスハラ対策をテーマにラウンドテーブル開催します!
5月29日(木)11:50~12:…

アイティフォー、コンタクトセンター向けカスハラ対策ソリューションの販売…
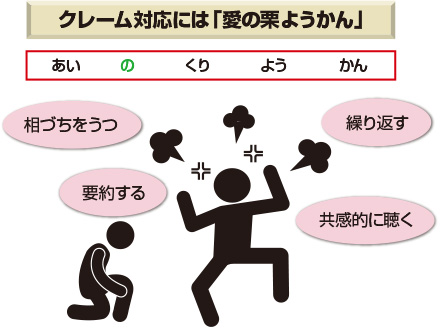
元ファーストクラスCAの接客術“おもてなし力”の磨き方
2025年1月号 <元ファーストクラスCAの接客術 “おもてなし力”の…
江上 いずみ