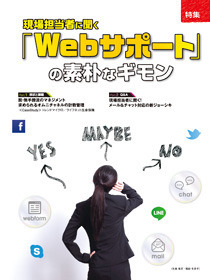
現場担当者に聞く
「Webサポート」の素朴なギモン
Part.1 <現状と課題>
脱・無手勝流のマネジメント
求められるオムニチャネルの計数管理
スマートフォンが普及し、コミュニケーション手段が多様化した今、「電話」の存在価値が揺らいでいる。消費者の多くはメールやチャット、メッセンジャーを好む傾向が強い。企業も、それらをサポート手段として採用しつつあるが、マネジメント手法は電話ほど成熟・共通性がなく、各社“無手勝流”に近いのが現状だ。Part.1では、各チャネルの特質やマネジメント最適化の「条件」をまとめる。
企業にわざわざ電話をかけたい消費者は存在しない。「電話」というコミュニケーションは、さほどプライオリティの高い手段ではなくなっている。電話を、顧客/消費者との関係作りにおける前提条件であり、ロイヤルティを高める有効な顧客接点と捉えるべきなのか──コンタクトセンターにおけるこれまでの「常識」を考え直す時期にきている可能性がある。
コンタクトセンターが顧客接点である以上、顧客のコミュニケーション手段が変われば、センターのマネジメントも変わって当然だ。図は、メール/チャット/メッセンジャー/電話の“適性”を評価したものだ。オムニチャネル時代といわれる今、常に同じチャネルを使う顧客は存在しない。パーソナリティ、シチュエーション、コンタクトする理由、そして過去の経験を踏まえて使うチャネルを決める。つまり、すべてをカバーすることで顧客の「選択」という要望にはほぼ応えることができるということだ。
この選択肢を用意し、顧客との距離感を最適化している事例として、チャット対応はトレンドマイクロ、LINE対応はライフネット生命保険を取材した。
図 顧客視点でみた「チャネルの選択」
※画像をクリックして拡大できます
CASE STUDY 1:トレンドマイクロ
<チャット対応>
ログ管理、リアルタイム監視も万全
対応精度と生産性の両立を図る

セキュリティエキスパート本部コンシューマテクニカルサポート部の大倉昌子シニアエンジニア
CASE STUDY 2:ライフネット生命保険
<メッセンジャー対応>
顧客層、距離感、生産性──
既存チャネルの弱点をことごとくカバー

営業本部お申し込みサポート部の森根光春氏(左)、鈴木大祐チームリーダー(右)
Part.2 <Q&A>
現場担当者に聞く!
メール&チャット対応の新ジョーシキ
メールやチャットといったノンボイス対応は、マネジメント、オペレーションともに電話対応のようなルールが確立されていない。現場では、経験を積みながらそれぞれの手法で運営しているのが現状だ。Part.2では、実際にメール/チャットセンターをマネジメントしている5名の管理者および、その手法をコーチングしているプロの視点で「よくある疑問」に回答してもらう。
顧客の「真の用件/真意」を引き出すことが顧客接点における満足度やロイヤルティを左右する。電話対応ならば、“リアルタイムの会話”でこの問題を解消できるが、メールやチャットといったテキストでのコミュニケーションの場合、短い文章から意図を読み取ることと並んで、相手を不快にさせない「文章力」を問うケースが多かった。採用も同様だ。
だが、オズビジョンの端野一郎氏は「文章力は育成できます」と主張する。さらに「相手の立場に立って物事を考える力、マインドは育成が難しいため、採用ではこちらを重視しています」と話す。
また、コールセンターのコンサルティングを行うY'sラーニングの浮島 由美子代表は「重要なのは、テンプレートを選ぶ能力」と説明する。これによって、読み書きのスピードも短縮できる。
“文章力”以上に重視すべきスキルがあるということだ。
チャット対応で見込める
投資対効果の可能性
チャット対応で疑問視されるのが、同時対応人数だ。GMOペパボとランサーズでは「顧客満足を考えると2名の同時対応が最適」としている。投資効果が出ないのではという見方もあるが、ランサーズでは、契約につながると予測される対応をモニタリングの中心に置き、経営貢献の道を探っている。
電話ではなく、メールやチャットを重視したセンター運営を実践し、かつビジネスも成長している5社のマネジメントにWebサポートにおいて運用上で浮上しやすい疑問を聞く。
回答者(順不同)
●山田 和弘 氏
メルカリ 執行役員
●宇賀神 卓馬 氏
GMOペパボ EC事業部カスタマーサービスグループ マネージャー
●冨樫 謙太郎 氏
ランサーズ カスタマーコミュニケーション マネージャー
●端野 一郎 氏
オズビジョン ハピタス事業部
●安信 竜馬 氏
エウレカ カスタマーケア統括マネージャー
●浮島 由美子 氏 <アドバイザー>
Y'sラーニング 代表
![]()
2024年01月31日 18時11分 公開
2017年03月20日 00時00分 更新