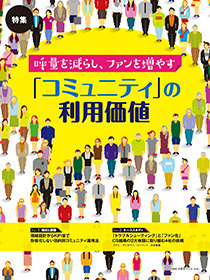
呼量を減らし、ファンを増やす
「コミュニティ」の利用価値
Part.1 <現状と課題>
導線設計からKPIまで
形骸化しない目的別コミュニティ運用法
「呼量削減」と、「継続利用」をもたらすCS向上。コールセンターに課されたこれらのミッションを同時に解決する手法として注目されつつあるのが「コミュニティ」だ。しかし、開設したものの形骸化して閉鎖、あるいは開店休業状態に陥る事例もある。Part.1では主にコミュニティ運用のコンサルタント、Part.2では事例企業への取材を通して“コミュニティ運用成功の道程”を検証する。
コロナ禍ではコールセンターの一時的な閉鎖や営業時間の短縮、新規感染者数が減ると採用難による人手不足──リソース管理が永遠の課題であることを再確認したコールセンター業界。そこで導入が相次いでいるのが、チャットボット、ボイスボット、FAQなどの自己解決ソリューションだ。
編集部が行った調査では、呼量削減、自己解決率向上を狙い、チャットボットの導入を検討している企業は74.6%を占める。しかし、実際にチャットボットやLINEボットに問い合わせた経験のある消費者に行った調査では、「チャットボットだけですぐに解決した」という回答は33.5%にとどまっている。すなわち、狙い通り自己解決に導いているとは言い難いのが実情だ。
企業の人的リソースを活用することなく、顧客の問題を解決するもう1つの手段として注目されつつあるのが「コミュニティ」だ。顧客同士での問題解決以外にも、VOC収集、顧客のファン化といったロイヤルティ向上など、さまざまなメリットがある。注意すべきは用途や目的によって運用手法が異なる点だ。図にそれぞれの効果や運用方法を整理した。本特集では、青枠内の2種類を取り上げる。
図 目的別、コミュニティ運用の概要
※画像をクリックして拡大できます
Part.2 <ケーススタディ>
「トラブルシューティング」と「ファン化」
CS組織の2大命題に取り組む4社の挑戦
企業が運用するコミュニティの主な目的が、サポートとファン化だ。Part.2では、サポートの事例としてさまざまなプラットフォームを利用するアドビ、サイボウズ、ローランドに、ファン化の事例として森永製菓に取材。それぞれのミッション、KPI、形骸化を防ぐ施策、社内での活用手法、リスクヘッジ方法など、具体的な運用の要諦を聞いた。
CASE STUDY 1:アドビ
「相互扶助」効果を最大化する
プロフェッショナル制度の運用


アドビのサポートコミュニティ画面
CASE STUDY 2:サイボウズ
サポート組織ではできない経営貢献
ミッションは共創型「エコシステム」の構築


「キンコミ」「アトツギカイギ」のトップページ
CASE STUDY 3:ローランド
電話窓口を閉鎖、サポートの柱の1つに
“助け合う力”を増幅する「報酬」の仕掛け
CASE STUDY 4:森永製菓
58万会員を擁するファンサイト
成功の秘訣は場づくりと双方向コミュニケーション

森永製菓「エンゼルPLUS」のトップページ
2024年01月31日 18時11分 公開
2022年07月20日 00時00分 更新